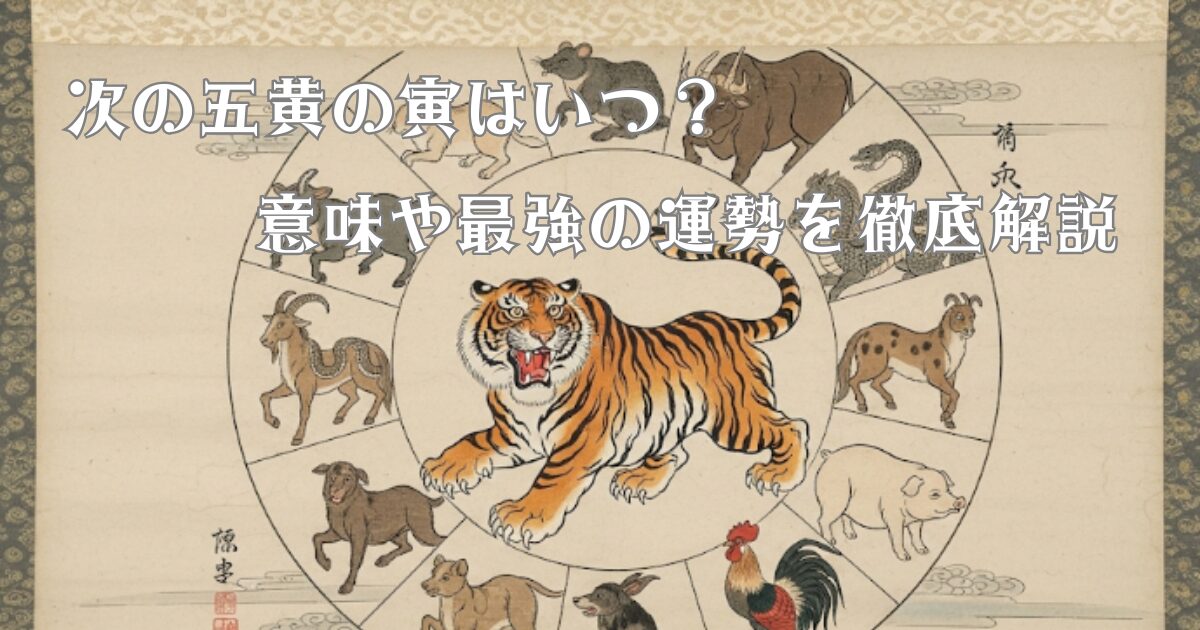「五黄の寅(ごおうのとら)」という言葉を耳にして、次の周期はいつなのか、どのような意味を持つのか、具体的な情報を探していませんか。
最強の運勢とも言われる一方で、「性格悪い」「やばい」といった少し怖い迷信も囁かれており、その実像が気になっている方も多いでしょう。
その読み方からスピリチュアルな意味、そしてよく比較される丙午との違いまで、多くの疑問があるかもしれません。
また、60年に一度と勘違いされがちなその周期は、正しくは何年に一度巡ってくるのでしょうか。
この記事では、五黄の寅が何年生まれ(西暦)の方に該当するのかを明確にし、その年に生まれた女性や男性の性格、全体的な運勢、そして気になる金運に至るまで、徹底的に深掘りして解説します。
さらに、該当する著名人、有名人、芸能人を具体的な例として挙げながら、この特別な干支が持つパワーの全体像を明らかにしていきます。
ぜひ最後までご覧ください。
- 五黄の寅の周期や西暦、基本的な意味
- 「最強」「やばい」と言われる理由と本当の性格
- 男女別の運勢や該当する有名人
- 丙午との違いや気になる金運
次の五黄の寅はいつ?意味と周期

五黄の寅という特別な年の本質を理解するためには、まずその言葉の成り立ちと、どれくらいの頻度で巡ってくるのかという基本的な知識が不可欠です。
ここでは、言葉の読み方や意味、そして周期について詳しく解説していきます。
- まずは五黄の寅の読み方と意味
- 60年に一度?周期と何年生まれか
- なぜ最強でやばいと言われるの?
- スピリチュアルな力の根源とは
- 性格悪いという迷信は本当?
まずは五黄の寅の読み方と意味
五黄の寅は、「ごおうのとら」と読みます。
これは単に「寅年」というだけではなく、「九星気学」と「十二支」という、古代中国を起源とする二つの異なる占術が特定の年に重なり合うことで生まれる、非常に稀でパワフルな巡り合わせを指します。
この二つの要素をそれぞれ理解することが、五黄の寅が持つ特別なエネルギーの本質を知るための第一歩となります。
九星気学における「五黄土星」
まず「五黄」とは、九星気学における「五黄土星(ごおうどせい)」を指します。
九星気学は、人々が生まれた年の九星によって運勢や性格、相性などを占う占術です。
九星には一白水星、二黒土星、三碧木星などがありますが、その中で五黄土星は方位盤の「中央」に位置し、他の八つの星すべてを支配・統括する役割を担っています。
このことから「帝王の星」とも呼ばれ、九星の中で最も強力で根源的なエネルギーを持つと考えられています。
その力は、万物を育み繁栄させる一方で、腐敗したものや古いものを破壊し、新たな始まりを促すという、創造と破壊の両極端の作用を司る存在です。
十二支における「寅」
一方の「寅」は、日本人にとって馴染み深い十二支の一つ、虎(とら)のことです。
十二支の中でも、虎は「百獣の王」として知られ、その勇猛果敢な姿から力強さ、勇気、決断力、そして強い生命力の象徴とされてきました。
そのため、寅年に生まれた人は正義感が強く、リーダーシップがあり、困難に立ち向かう強靭な意志と行動力を持つと言われています。
五黄の寅の正体とは? 二つの「王」の融合
つまり五黄の寅とは、「帝王の星」である五黄土星の支配する年に、「百獣の王」である寅年が重なることを意味します。
中心から動かずにすべてを支配する「静」の力と、自ら行動し道を切り開く「動」の力、この二つの「王」の力が融合することで、他に類を見ない「最強」の運勢が生まれるとされているのです。
60年に一度?周期と何年生まれか
五黄の寅は、しばしば「60年に一度」と勘違いされることがありますが、これは還暦(60年で干支が一巡する)の周期と混同されたもので、正しくは36年に一度の周期で巡ってきます。
この周期は、数学的な必然性から生まれます。
九星気学が9年で一巡するのに対し、十二支は12年で一巡します。
この9と12の最小公倍数が36であるため、「五黄土星」の年と「寅年」が重なるのは36年に一度となるのです。
言い換えれば、3回に1回の寅年だけが、この特別な五黄の寅の年にあたります。
ご自身やご家族が該当するかどうか、これまでの五黄の寅の年と、次に訪れる年を西暦で確認してみましょう。
| 回 | 西暦(元号) | 該当年生まれの年齢(2025年時点) | その年に起きた主な出来事 |
|---|---|---|---|
| 前回 | 1986年(昭和61年) | 39歳 | チェルノブイリ原発事故、男女雇用機会均等法施行 |
| 前々回 | 1950年(昭和25年) | 75歳 | 朝鮮戦争勃発、警察予備隊令公布 |
| 3回前 | 1914年(大正3年) | 111歳 | 第一次世界大戦勃発、桜島の大噴火 |
| 前回 | 2022年(令和4年) | 3歳 | 北京冬季五輪開催、ロシアのウクライナ侵攻 |
| 次回 | 2058年(-) | – | – |
このように、直近では2022年が五黄の寅でした。
表を見ると、五黄の寅の年には社会を揺るがす大きな出来事が起きていることも分かります。
そして、その次にこの特別な年が訪れるのは2058年となります。
なぜ最強でやばいと言われるの?
五黄の寅が「最強」あるいは「やばい」とまで表現される理由は、その成り立ちに由来する、他に例を見ないほどの圧倒的なエネルギーの質にあります。
前述の通り、五黄土星は「万物を支配し、時には破壊して再生を促す帝王の力」を持っています。
この力は、安定や調和よりも、根本的な変革をもたらす性質があります。
一方、寅年は「目標に向かって突き進む決断力と、困難をものともしない行動力」という、百獣の王の力を象徴します。
この二つが掛け合わさることで、単なるリーダーに留まらない、時代を動かすほどのカリスマ性と実行力が生まれると考えられているのです。
ただ、この常人離れした強すぎるエネルギーは、時として制御が難しい「両刃の剣」となります。
この「やばい」という現代的な言葉は、五黄の寅の性質を的確に表しているかもしれませんね。
良い意味で「桁外れにすごい」という圧倒的な成功をもたらす力と、悪い意味で「手に負えないほど強烈で破滅的」になりかねない危うさ。
その両方の側面を併せ持っているのです。畏敬の念と、少しの恐れを込めて「やばい」と呼ばれているのでしょう。
例えば、その揺るぎない信念は、大きな事業を成功に導く原動力となる一方で、周囲の意見を聞き入れない独善に陥る危険性も秘めています。
また、一度決めたことをやり遂げる圧倒的な行動力は、時として周囲から見ると「強引」「自己中心的」と映り、軋轢を生んでしまうことがあるのです。
この極端さが、「最強」であり「やばい」と評される所以です。
スピリチュアルな力の根源とは

五黄の寅が持つスピリチュアルな力の根源を深く探ると、「中央という絶対的な軸」と「荒ぶるほどの生命力」という、二つの対照的なキーワードに集約されます。
まず、五黄土星が位置するのは、九星方位盤の「中央」、すなわち「太極」と呼ばれる宇宙の中心です。
ここは全てのエネルギーが発生し、循環していく根源的な場所とされています。
中央は動かずに全体を支配し、周囲に秩序をもたらす「静」の力を象徴します。これは、五黄の寅の人が持つ自分という確固たる軸、何事にも揺るがない精神的な強さの源となっているのです。
対して、十二支の寅(虎)は、原野を駆け巡る活動的で勇敢な「動」の力を象徴します。
これは、目標に向かって貪欲に突き進む実行力や、困難を乗り越えるための旺盛な生命力の源となります。
この静と動、一見すると相反する二つの強大なエネルギーが一人の人間の中で融合することで、他に類を見ない特別なカリスマ性が生まれると考えられています。
言葉の響きも影響している?
ちなみに、その力強いイメージは言葉の響きにも影響されているという説があります。
「ごおう」という音が、「剛(ごう)」や「強(ごう)」といった強さを意味する漢字を連想させることが、この概念が複雑な占術の知識なしに民衆に広まる一因になったのかもしれません。
言葉の持つイメージも、スピリチュアルな力強さを無意識のうちに補強しているのです。
性格悪いという迷信は本当?
「五黄の寅は性格が悪い」という迷信を耳にすることがありますが、これはその性質を一面的な視点から誤解した表現と言えるでしょう。
より正確に表現するならば、「非常に強い独立心とプライド、そして揺るぎない信念を持っているため、時として周囲に誤解されたり、衝突したりしやすい」と捉えるべきです。
五黄の寅の人の行動原理は、常に自分の中にある強い正義感や信念に基づいています。
そのため、組織の論理や他人の意見に安易に流されたり、自分の信念を曲げてまで誰かに媚びへつらったりすることを良しとしません。
この妥協のない姿勢が、協調性を重んじる文化や場面においては「頑固」「わがまま」「空気が読めない」と見なされ、「性格が悪い」という不当なレッテルを貼られてしまうことがあるのです。
強さゆえの「生きづらさ」と成長
この強すぎる個性のために、特にエネルギーが未熟な若い頃は、周囲の無理解や反発に苦しみ、多くの苦労や孤独を経験する傾向があるとされています。
しかし、その逆境や試練こそが彼らをさらに鍛え上げ、乗り越える過程で人間的な深みと、他者を思いやる優しさを兼ね備えた「本物の強さ」を手に入れるとも言われています。
したがって、「性格が悪い」のではなく、「誰にも依存せず、媚びることなく、確固たる自分という指針を持って生きている」というのが、より彼らの実像に近い表現です。
その姿は、見る人によっては非常に魅力的で頼もしく映るでしょう。
五黄の寅はいつ生まれ?運勢と人物像
五黄の寅の基本的な意味を理解したところで、次に気になるのは「その年に生まれた人は具体的にどんな人なのか」ということでしょう。
ここでは、男女別の詳しい人物像や、該当する著名人、そして運勢について深く掘り下げていきます。
- 五黄の寅に生まれた女性と男性
- 該当する著名人・有名人・芸能人
- 丙午の迷信との違いを徹底比較
- 全体運勢と気になる金運について
五黄の寅に生まれた女性と男性
五黄の寅に生まれた人々は、共通してパワフルなエネルギーを持ちますが、その発揮のされ方には男女で少し異なる傾向が見られます。
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
女性の特徴:時代と共に評価が変わる先駆者

五黄の寅の女性は、その人物像の評価が時代と共に劇的に変化した、象徴的な存在です。
かつては「気が強すぎて夫を尻に敷き、家庭を顧みない」とされ、結婚相手として敬遠されるという悲しい迷信がありました。
これは、女性の自己主張が良しとされなかった家父長制の価値観を反映したものでした。
しかし、女性の社会進出が進んだ現代では、その評価は180度一変しています。
かつて欠点とされた強い意志、卓越したリーダーシップ、高い自立心は、現代社会でキャリアを築き、成功を収めるための大きな武器と見なされるようになりました。
仕事では持ち前のカリスマ性を発揮して重要なポジションで活躍し、多くの人を惹きつけます。
恋愛においては深く情熱的で、一度愛した相手には一途な愛情を注ぎますが、同時に独占欲が強くなる一面も。
物静かな見た目に反して、内面には誰よりも熱い情熱と深い愛情を秘めている人が多いとされています。
価値観の変化と1986年の五黄の寅
興味深いことに、前回の五黄の寅の年である1986年(昭和61年)は、男女雇用機会均等法が施行された年でもあります。
女性の社会での活躍が本格的に始まったこの年に生まれた世代が、現代の「自立した強い女性像」を体現しているのは、単なる偶然ではないのかもしれません。(出典:厚生労働省)
男性の特徴:静かなる実力派リーダー

五黄の寅の男性は、「マイペースを貫く静かな実力者」と評されることが多いです。
大声で人をまとめるタイプではなく、口数は少なく物静かな印象を与えることが多いでしょう。
しかし、その内には常人の数倍とも言われる驚異的な気力と体力を秘めており、一度決めた目標は何があってもやり遂げます。
人に指図されたり、管理されたりすることを極端に嫌い、常に自らの信念と判断に基づいて行動します。
派手な自己アピールはしませんが、その確かな実力と結果を出す行動力で周囲を納得させ、自然と「あの人についていけば間違いない」と思わせるリーダーシップを発揮します。
特に、様々な経験を積む30歳を過ぎてから、その強靭な意志とぶれない軸が社会的な成功や高い地位に結びつきやすいと言われています。
該当する著名人・有名人・芸能人
「百聞は一見に如かず」と言いますが、五黄の寅の年には、その特性をまさに体現するような、各界で圧倒的な存在感を放つ著名人、有名人、芸能人が数多く生まれています。
その一部をご紹介します。
1950年(昭和25年)生まれ
日本の戦後復興期に生まれ、その後の高度経済成長を第一線で牽引した世代です。
まさに「パワー」と「生命力」という言葉がふさわしい方々が揃っています。
- 和田アキ子さん:
芸能界のご意見番として、誰にも媚びない姿勢を貫く姿は五黄の寅の象徴的です。 - 故・志村けんさん:
お笑いの世界で独自のスタイルを確立し、国民的な人気を博したカリスマです。 - 舘ひろしさん:
ダンディで揺るぎない独自の美学を持つ俳優。 - 久石譲さん:
世界的な作曲家として、唯一無二の世界観を創り上げています。 - 池上彰さん:
ジャーナリストとして、難しいニュースを自身の言葉で分かりやすく解説する第一人者です。
その他、梅沢富美男さん、八代亜紀さんなどもこの年に生まれています。
1986年(昭和61年)生まれ
日本が経済的な自信の絶頂にあったバブル期に生まれ、その後の「失われた時代」という変革期を生き抜いてきた世代です。
特に女優やアスリートに、自分のスタイルを確立した方々の活躍が目立ちます。
- 北川景子さん、石原さとみさん、杏さん:
人気と実力を兼ね備え、自らのキャリアを主体的に切り開く現代的な女優の代表格です。 - 本田圭佑さん:
独自の哲学と強い信念でサッカー界を突き進む、まさに「マイペースなリーダー」です。 - ダルビッシュ有さん:
メジャーリーグで活躍する投手。常に自分をアップデートし続ける探究心と発信力が特徴です。
その他、上野樹里さん、安藤サクラさん、沢尻エリカさんなども1986年生まれです。
これらの顔ぶれを見ると、組織の調和を重んじるというよりは、個人の圧倒的な才能やカリスマ性で道を切り開いてきた方が多いことに気づきます。
これは、五黄の寅の持つ「個の強さ」が最大限に発揮された結果と言えるでしょう。
丙午の迷信との違いを徹底比較

「強い女性」に関する干支の迷信として、五黄の寅と必ずと言っていいほど比較されるのが「丙午(ひのえうま)」です。
どちらも女性にまつわる強い言い伝えがありますが、その性質、そして社会に与えた影響は大きく異なります。
丙午の迷信は「丙午生まれの女性は気性が激しく、夫を食い殺す(早死にさせる)」という非常に強烈なもので、単なる言い伝えでは終わりませんでした。
実際に、直近の丙午であった1966年には、日本の出生数が前年に比べて約25%も激減するという、異常な事態が発生しました。
これは、迷信を信じた人々がこの年の出産を意図的に避けたことを示す、社会的なデータとして明確に残っています。(出典:厚生労働省「出生の年次推移」)
両者の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 五黄の寅 | 丙午 |
|---|---|---|
| 周期 | 36年に一度 | 60年に一度 |
| 迷信の内容 | 気が強く、夫を尻に敷く (性格的特性) | 気性が激しく、夫を食い殺す (運命的呪い) |
| 社会的影響 | 出生率の明確な低下は見られない | 1966年の出生率が前年比で約25%激減 |
| 現代の解釈 | 「自立した強い女性」としてポジティブに再評価 | ネガティブなイメージが根強く、再解釈の余地が少ない |
この比較から分かる最大の違いは、丙午が「避けがたい運命的な呪い」として人々に恐れられ、実際の人口動態にまで影響を与えたのに対し、五黄の寅はあくまで「性格的な特性」として捉えられてきた点です。
そのため、時代の価値観が「強い女性」を肯定的に捉えるように変わるにつれて、五黄の寅の「気が強い」という特徴は欠点から長所へと見事に転化し、現代でもその力強い伝承が生き続けているのです。
全体運勢と気になる金運について
五黄の寅という特別なエネルギーは、その年に生まれた人の性格だけでなく、年そのものの運勢や、個人の人生における金運にも大きな影響を与えるとされています。
全体運勢:社会が動く「破壊と再生」の年
五黄の寅の年は、五黄土星の持つ「破壊と再生」の性質が社会全体に強く表れるため、既存の秩序や価値観が大きく揺らぐ、激動の年になりやすいと言われています。
前のセクションの表で見たように、過去の五黄の寅の年には世界大戦や大きな紛争、社会制度の変革など、歴史の転換点となる出来事が起きています。
個人にとっても、この年は現状維持が難しく、仕事、人間関係、住まいなど、人生の根幹に関わる重要な決断を迫られる一年となるでしょう。
周到な準備をしてきた人にとっては、この大きな変化の波に乗って大飛躍する絶好のチャンスとなります。
一方で、変化を恐れて行動しない人には、厳しい試練が訪れるかもしれません。
いずれにせよ、行動と決断が求められる、パワフルな一年であることは間違いありません。
金運:「稼ぐ力」と「使う力」が桁外れ

五黄の寅生まれの人の金運は、その性格を反映して「超ハイリスク・ハイリターン」な傾向が顕著です。
生まれ持った強いエネルギーと行動力、そしてリーダーシップを活かして、若いうちから大きなお金を稼ぎ出す才能に恵まれています。
組織の中で出世するだけでなく、自ら事業を起こして成功を収める人も少なくありません。
五黄の寅の金運まとめ
五黄の寅の人は、節約してコツコツと貯蓄をすることにはあまり興味がありません。
それよりも、自らの才覚と行動で大きく稼ぎ、それを自己投資や事業拡大、あるいは自分の好きなことに大胆に使うことに喜びと価値を見出すタイプです。
その強い運勢と勝負勘を活かせば、一代で莫大な富を築く可能性があります。
しかし、その一方で自信過剰から無謀な投資に手を出したり、人の忠告を聞かずに大勝負に出て失敗したりするリスクも常に伴います。
まさに、お金の面でも波乱万丈な運勢と言えるでしょう。
まとめ:次の五黄の寅はいつ来る?
最後に、この記事で解説してきた五黄の寅に関する要点をリスト形式でまとめます。
最強の干支とも言われるこの特別な年の意味や、該当する人々の魅力、そして次に訪れる時期についての理解が深まっていれば幸いです。
- 五黄の寅は「ごおうのとら」と読む
- 九星気学の「五黄土星」と十二支の「寅」を組み合わせた特別な干支
- その周期は数学的な理由から36年に一度巡ってくる
- 直近の五黄の寅は1950年、1986年、2022年であった
- 次に五黄の寅が訪れるのは西暦2058年
- 「帝王の星」と「百獣の王」の力が融合した最強の運勢とされる
- その強烈なエネルギーから畏敬の念を込めて「やばい」とも言われる
- 基本性格は強い信念とカリスマ性を持つ生まれながらのリーダー気質
- その頑固さや独立心から「性格悪い」と誤解されることもある
- 女性像は時代と共に評価が変わり現代では「時代の先駆者」と見なされる
- 男性像は多くを語らず実力で人を惹きつける「静かなるリーダー」
- 和田アキ子さんや本田圭佑さんなど各界に多くの有名人を輩出している
- 丙午の「呪い」とは異なり時代の価値観で再解釈される「特性」である
- 金運は大きく稼ぐ力を持つが大胆な勝負に出やすく波乱万丈な傾向
- 五黄の寅の年は社会全体が大きく動く歴史的な転換点になりやすい
五黄の寅の持つ意味やその強さ、そして人物像について、多角的に解説してきました。
単なる迷信として片付けるのではなく、その背景にある人々の畏敬の念や、時代と共に変化してきた価値観を知ることで、この特別な干支が持つ奥深さを感じていただけたのではないでしょうか。
ご自身が五黄の寅の方はもちろん、周りに該当する方がいらっしゃる場合も、その強さの裏にある本質を理解することで、新たな一面が見えてくるかもしれません。
この記事が、あなたの五黄の寅に対する理解を深める一助となれば幸いです。