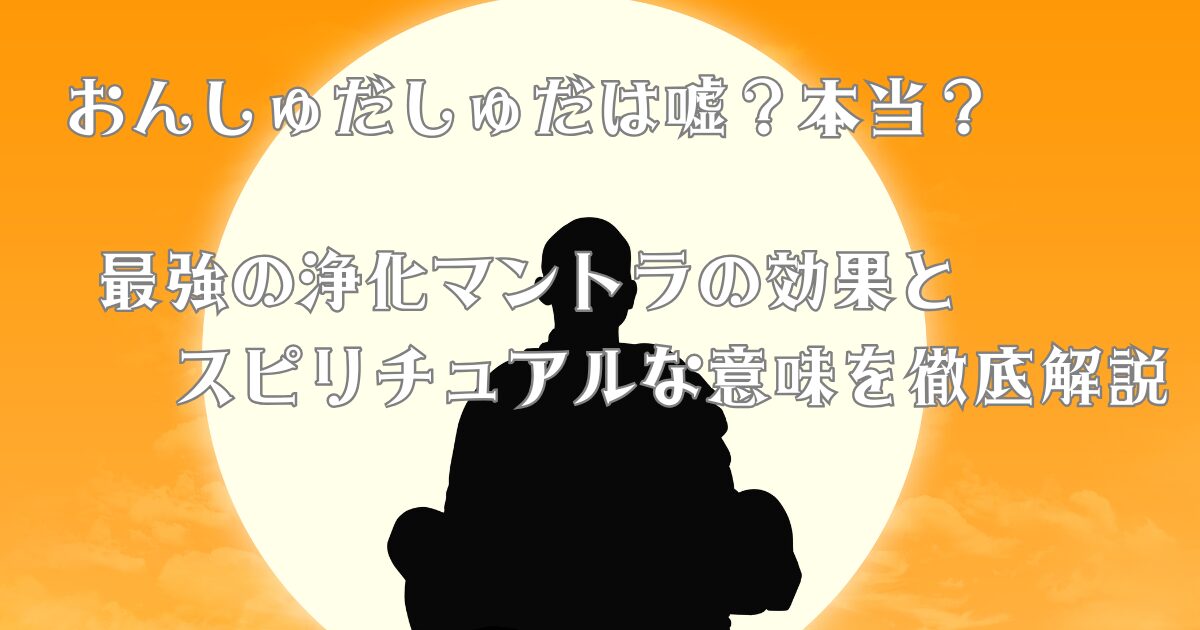「おんしゅだしゅだ」
この不思議な響きの言葉を、あなたはどこで耳にしましたか?
SNSで「金運が上がる最強のマントラ」として紹介されていたかもしれません。
あるいは、スピリチュアルな世界で「唱えるだけで人生が変わる」と聞き、その効果に半信半疑ながらも強く惹かれているのかもしれません。
しかし、その一方で「おんしゅだしゅだは嘘だ」「根拠がない」といった声も目にし、「一体、何が本当なの?」と混乱しているのではないでしょうか。
ご安心ください。
この記事は、そんなあなたのためのものです。
この記事では、単なる噂や断片的な情報ではなく、「おんしゅだしゅだ」の真実を、その本質から徹底的に解き明かしていきます。
サンスクリット語の意味や空海との歴史的背景といったスピリチュアルな側面から、効果を最大化する正しい唱え方や最適な回数、そして多くの人が気になる金運への影響まで、あなたが抱える全ての疑問に、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。
この記事を読み終える頃には、「おんしゅだしゅだ」への疑いは確信に変わり、その絶大な浄化の力を、あなたの人生に取り入れる準備が整っているはずです。
さあ、最強の浄化マントラがもたらす、新しい世界の扉を開きましょう。

私も実際に唱えてみました!
仕事のプレッシャーで心がザワザワして眠れない夜があったんですが、試しに5分くらい静かに唱えてみたら、本当にスーッと落ち着いて…。その日はぐっすり眠れたんです。
短い言葉だからすごく集中しやすくて、これなら続けられそうだなって思いましたよ!
- おんしゅだしゅだの本当の効果と「嘘」と言われる理由
- 初心者でもすぐできる正しい唱え方・最適な回数
- 金運アップに繋がるスピリチュアルな仕組み
- 唱える際の注意点や、印・梵字に関する疑問
- 弘法大師・空海との知られざる歴史的背景
【実践編】おんしゅだしゅだの凄い効果と正しい唱え方


ここからは、いよいよ「おんしゅだしゅだ」をあなたの日常に取り入れるための、具体的な実践編に入ります。
「本当に効果があるの?」「どうやって唱えればいい?」「何回唱えるのがベストなの?」――多くの人が抱くこうした疑問に、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。
心と体を清める驚くべき浄化の力から、初心者でも簡単にできる正しい唱え方、そして「効果は嘘だ」という噂の真相まで。
この章を読めば、あなたも今日から自信を持って「おんしゅだしゅだ」を実践できるようになるはずです。
まずは、その最も根源的でパワフルな効果から見ていきましょう。
【効果】心身を浄化するスピリチュアルな力
「おんしゅだしゅだ」という真言が持つ最も根源的な力、それは心と身体、そしてエネルギーレベルでの「浄化」です。
まるで淀んだ水が澄み渡るように、私たちの内側に溜まった不要なものを取り除き、本来のクリアな状態へと導いてくれると言われています。
これは単なる気休めではなく、音の響き(波動)と、言葉に宿る意含(言霊)がもたらすスピリチュアルな作用です。
具体的には、以下のような効果が期待されています。
心の浄化:思考のノイズを止め、感情を穏やかにする
日々の生活で、頭の中が様々な考え事でいっぱいになり、思考が止まらない感覚はありませんか?
「おんしゅだしゅだ」を唱えることは、この思考の渦(モンキーマインド)を鎮めるのに役立ちます。
「しゅだ」という清らかな響きに意識を集中させることで、頭の中のおしゃべりが静まり、心が穏やかな湖面のように落ち着いていくのを感じるでしょう。
また、知らず知らずのうちに溜め込んでしまった怒りや不安、嫉妬といったネガティブな感情を洗い流す「魂のシャワー」のような役割も果たします。
特に人間関係で疲れた日の夜や、理由もなく心がモヤモヤする朝に唱えることで、感情のデトックスを促し、心の平穏を取り戻す手助けとなります。
身体の浄化:深いリラックスと緊張の緩和
この真言を唱えるときの独特な音の振動は、私たちの身体にも直接働きかけます。
声に出して唱えることで生まれる微細なバイブレーションが、身体の緊張を内側から優しくほぐしてくれるのです。
深い呼吸とともに「おん・しゅだ・しゅだ」と繰り返すことで、乱れがちな自律神経のバランスが整い、心身がリラックスモード(副交感神経優位)に切り替わります。
ストレスで硬くなった肩の力が抜けたり、寝つきが良くなったりといった身体的な変化を実感する人も少なくありません。
エネルギーの浄化:オーラを清め、本来の輝きを取り戻す
スピリチュアルな観点では、私たちには目に見えないエネルギー体(オーラ)があると考えられています。
人混みやネガティブな環境にいると、このオーラが曇ったり、不要なエネルギーが付着したりすることがあります。
「おんしゅだしゅだ」は、このエネルギーフィールドを浄化する強力なツールです。
まるでホワイトセージを焚いて空間を浄化するように、この真言はあなた自身のエネルギーを清め、邪気を払い、本来の輝きを取り戻すサポートをしてくれるでしょう。
このように、「おんしゅだしゅだ」の浄化作用は多岐にわたります。まずはこの浄化効果を実感することが、次に解説する金運アップや願望実現といった、より現実的な変化を引き寄せるための大切な土台となるのです。
金運アップや願望実現も期待できるって本当?


「おんしゅだしゅだを唱えると、金運が上がる」「願いが叶う」――そんな魅力的な話を耳にしたことがあるかもしれません。
しかし、これは「唱えるだけでお金が降ってくる」といった魔法の呪文とは少し違います。
おんしゅだしゅだが金運や願望実現に繋がるというのは、間接的な効果として捉えるのが正しい理解です。
そのメカニズムは、スピリチュアルな観点から見ると非常に合理的です。
なぜ金運に繋がるのか?「浄化」がもたらす豊かさのサイクル
金運や豊かさは、スピリチュアルな世界では「エネルギーの流れ」として捉えられます。
お金の流れが滞っている人は、多くの場合、自分自身の中に何らかのエネルギー的な詰まりや、お金に対するネガティブな思い込み(メンタルブロック)を抱えています。
- 「自分はお金持ちになる価値がない」
- 「お金は苦労しないと手に入らない」
- 「お金を使うことに罪悪感がある」
このような無意識のブロックが、豊かさの流れをせき止めてしまうのです。
ここで「おんしゅだしゅだ」の出番です。この真言が持つ強力な浄化作用は、こうしたお金に対するネガティブな思い込みや、過去の失敗からくる恐れの感情を洗い流す手助けをしてくれます。
心が浄化され、クリアな状態になると、不思議と以下のような変化が起こり始めます。
- 直感が冴える: 良いチャンスや情報に気づきやすくなる。
- 判断力が向上する: 衝動買いや無駄遣いが減り、賢いお金の使い方ができる。
- 行動力が高まる: 副業を始めたり、新しいスキルを学んだりと、豊かさに繋がるアクションを起こせる。
つまり、あなた自身の波動が整うことで、豊かさの波動と共鳴しやすくなるのです。
これが、おんしゅだしゅだが金運アップに繋がると言われる本当の理由です。
願望実現への道筋をクリアにする
願望実現も同様のメカニズムです。
「願いが叶わない」と感じるとき、多くの場合、心の奥底で「どうせ無理だ」という疑いや諦めの気持ちが、願望のエネルギーを打ち消しています。
おんしゅだしゅだを唱える習慣は、この心のノイズを取り除き、「本当に望むこと」に意識を集中させる訓練になります。
心が静まり、自分の本当の望みが明確になると、潜在意識がその実現に向けてフル稼働を始めます。
必要な情報が目に飛び込んできたり、協力者が現れたりと、まるで宇宙が味方してくれているかのようなシンクロニシティ(意味のある偶然の一致)が起こりやすくなるでしょう。
結論として、おんしゅだしゅだは「打ち出の小槌」ではありません。
しかし、あなたの内面を整え、金運や幸運を引き寄せる「磁石」のような体質へと変えてくれる、非常にパワフルなサポートツールなのです。
大切なのは、真言の力を信じつつも、現実世界での行動とセットで考えることです。
「効果は嘘」と言われる理由と正しい向き合い方
「おんしゅだしゅだ」の持つスピリチュアルな力に心惹かれる一方で、インターネット上では「効果なんて嘘」「ただのデマだ」といった否定的な声も目にします。
なぜ、このように言われてしまうのでしょうか?
その背景には、いくつかの誤解と、情報の広まり方に理由があります。
ここで冷静にその原因を探り、私たち自身がどう向き合っていくべきかを考えてみましょう。
「嘘」だと言われる3つの主な理由
- 公式な経典に出典が見当たらない
最も大きな理由がこれです。「おんしゅだしゅだ」は、仏教の公式な経典(お経)の中に、その出自や意味が明確に記されているわけではありません。
また、「空海が広めた最強の真言」という話も、空海自身の著作物で確認できるものではなく、後世に伝わる過程で生まれた伝承の可能性が高いとされています。
この「出典不明」という点が、「誰かが創作した嘘ではないか?」という疑念に繋がっているのです。 - 効果が過度に誇張されている
SNSや一部のウェブサイトでは、「唱えるだけで人生が激変!」「宝くじが当たった!」といった、あまりにも劇的な効果が語られることがあります。
このような非現実的な体験談は、かえって胡散臭さを生み出し、「そんなうまい話があるはずない、嘘に決まっている」という反発を招く原因となります。 - 即効性を期待しすぎてしまう
魔法の呪文のように、唱えたらすぐに目に見える結果が出ることを期待してしまうと、何も変化が起きなかったときに「やっぱり効果はなかった、嘘だった」と結論づけてしまいがちです。
真言やマントラは、本来、継続的な実践を通じて内面をゆっくりと変容させていくものです。
即効性を求める心そのものが、効果を感じにくくさせ、失望に繋がるケースは少なくありません。
【結論】「嘘か本当か」を超えた、正しい向き合い方とは
では、私たちは「おんしゅだしゅだ」とどう付き合っていけば良いのでしょうか。
大切なのは、「嘘か本当か」という二元論で判断するのをやめることです。
- 「万能薬」ではなく「心のサプリメント」と捉える
おんしゅだしゅだは、病気を治す特効薬ではありません。
しかし、日々の心の健康をサポートし、コンディションを整えてくれる「サプリメント」のようなものだと考えてみてください。
サプリメントが即効性はないけれど、続けることで体調を整える手助けになるように、この真言も、続けることで心の免疫力を高め、ストレスに強い自分を育む手助けとなります。
- 一番の基準は「あなた自身の感覚」
他人が「嘘だ」と言おうと、「凄い効果がある」と言おうと、最も信頼すべきはあなた自身の感覚です。
実際に唱えてみて、「なんだか心地よい」「心が少し軽くなる気がする」と感じるのであれば、それはあなたにとって「本当」の効果です。
逆に、義務感で唱えて苦しくなるのであれば、無理に続ける必要はありません。
- 依存せず、現実を生きるためのツールとして活用する
最も健全な向き合い方は、おんしゅだしゅだに全てを委ねて現実逃避するのではなく、現実をより良く生きるための「補助ツール」として活用することです。
心を浄化し、エネルギーを整えた上で、現実的な行動を起こしていく。
その時、この真言はあなたの背中をそっと押してくれる、心強い味方となってくれるでしょう。
【唱え方】効果を最大化する正しい方法・回数・時間


おんしゅだしゅだの効果を最大限に引き出すためには、ただ言葉を繰り返すだけでなく、いくつかのポイントを押さえた「丁寧な唱え方」を意識することが大切です。
ここでは、誰でも簡単に始められる基本的な方法から、効果を高める回数や時間帯までを具体的に解説します。
まず、できるだけ静かで誰にも邪魔されない環境を選びましょう。自室のベッドの上や、落ち着けるリビングのソファなど、心からリラックスできる場所が最適です。
- 楽な姿勢で座る: あぐらでも、椅子に座っても構いません。背筋を軽く伸ばし、身体の力を抜きます。
- 目を閉じる: 視覚からの情報をシャットアウトすることで、意識を内側に向けやすくなります。
- 深呼吸をする: 鼻からゆっくり息を吸い込み、口から静かに長く吐き出します。これを3回ほど繰り返し、心を落ち着かせます。
準備が整ったら、いよいよ真言を唱え始めます。
- 発音: 「おん・しゅだ・しゅだ」と、一音一音をはっきりと、しかし優しく発音することを意識します。特に「おんー」は少し伸ばし、身体の中心から響かせるようなイメージで唱えると良いでしょう。
- リズム: 急ぎすぎず、ゆっくりとした一定のリズムを保ちます。自分の心拍と同じくらいのペースをイメージすると、心地よく続けられます。
- 声の大きさ: 大きな声を出す必要はありません。自分が聞いていて心地よいと感じる、ささやくような声量で十分です。周りの状況が許さない場合は、声に出さず**心の中で静かに唱える(黙想・心念)**だけでも効果はあります。大切なのは、音の響きに意識を集中させることです。
唱える回数に厳密な決まりはありませんが、古くから仏教で意味を持つとされる数字を目安にすると、意識を集中させやすくなります。
- 初心者向け(まずはここから):3回、7回
- まずは短くても良いので、毎日続けることが大切です。3回や7回なら、1分もかからずに実践できます。
- 慣れてきたら:21回
- 少し集中力を高めたい時におすすめの回数です。真言の響きが身体に染み渡る感覚を得やすくなります。
- より深く実践したい時:108回
- 108は人間の煩悩の数とされ、これを唱えることで煩悩を浄化するという意味合いがあります。数珠を使いながら1玉ずつ唱えていくと、深い瞑想状態に入りやすくなります。
時間はどれくらい?
時間で区切るなら、まずは5分間から始めてみましょう。
タイマーをセットして、時間内はひたすら真言を繰り返すことに集中します。
無理のない範囲で、徐々に時間を延ばしていくのが継続のコツです。
おすすめの時間帯は?
いつ唱えても構いませんが、特におすすめの時間帯があります。
- 朝(起床後): 1日の始まりに心をクリアにし、ポジティブなエネルギーでスタートを切るため。
- 夜(就寝前): 1日のうちに溜まったストレスやネガティブな感情を浄化し、安らかな眠りにつくため。
- その他: 仕事でストレスを感じた時、人間関係で心が揺れた時など、「浄化したい」と感じたその瞬間に、数回唱えるだけでも効果的です。
【応用】印の結び方・梵字・待ち受けについて
基本的な唱え方に慣れてきたら、次にもっと深く「おんしゅだしゅだ」の世界に繋がりたいと感じるかもしれません。
ここでは、そうした思いに応えるための応用的な実践方法として、「印」「梵字」「待ち受け」について解説します。
印の結び方:「おんしゅだしゅだ」専用の印はある?
まず結論からお伝えすると、「おんしゅだしゅだ」を唱えるための専用の印(手印)というものは、公式には定められていません。
特定の仏様と一対一で対応する真言には決まった印があることが多いですが、「おんしゅだしゅだ」は浄化という概念そのものに働きかける言葉のため、特定の印と結びついてはいないのです。
しかし、がっかりする必要はありません。
真言を唱える際に、浄化や瞑想の効果を高めるサポートとなる基本的な印を取り入れることは非常に有効です。


- 合掌(がっしょう):
最もシンプルで基本となる姿勢です。
胸の前で両手を合わせることで、心が静まり、感謝と敬意の念が生まれます。どの真言を唱える際にも基本となる、パワフルな印です。 - 法界定印(ほっかいじょういん):
座禅の際に組まれることで有名な印です。
左手の上に右手を重ね、両手の親指の先を軽くつけます。
おへその下あたり(丹田)に置くことで、心が深く落ち着き、瞑想状態に入りやすくなります。
「おんしゅだしゅだ」を落ち着いて長く唱えたい時におすすめです。
無理に難しい印を組む必要はありません。まずは基本の合掌から始めて、心地よいと感じる形を取り入れてみてください。
梵字について:「おんしゅだしゅだ」を表す文字は?
こちらも同様に、「おんしゅだしゅだ」という言葉そのものを一文字で表す特定の梵字(種字)はありません。
これは、「しゅだ」がサンスクリット語の「śuddha(清浄な)」という単語の音を写した言葉であるためです。
しかし、ここでも関連するシンボルをイメージすることで、真言の効果を高めることができます。
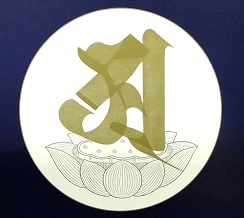
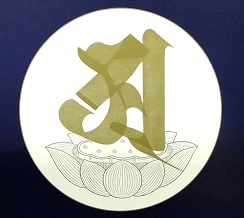
おすすめは、すべての始まりと宇宙の根源を象徴する「阿字」の梵字です。
密教において「阿字」は宇宙の真理そのものである大日如来を象徴し、あらゆるものの根源とされる最も神聖な文字です。
この「阿字」を心に思い浮かべながら「おんしゅだしゅだ」を唱えることで、より根源的なレベルでの浄化に繋がると考えられます。
待ち受けについて:浄化のエネルギーを持ち歩く
日常的に浄化の意識を保つために、スマートフォンの待ち受け画像を活用するのも素晴らしい方法です。
「おんしゅだしゅだ」専用の公式な待ち受け画像はありませんが、あなた自身が「清らかさ」や「浄化」を感じる画像を選ぶことで、そのエネルギーを常に受け取ることができます。
例えば、以下のような画像がおすすめです。
- 蓮の花: 泥の中から美しい花を咲かせる蓮は、まさに「浄化」と「目覚め」の象徴です。
- 澄み切った水や空: 見るだけで心が洗われるような、清流や青空、満点の星空の写真。
- キラキラと輝く光: 光のシャワーや、木漏れ日のような、浄化のエネルギーをイメージさせる画像。
- 「阿字」の梵字: 先ほど紹介した「阿字」の梵字を待ち受けにするのも、強力なお守りとなるでしょう。
大切なのは、他人が良いという画像ではなく、あなた自身が心から「きれいだな」「心地よいな」と感じる一枚を選ぶことです。
スマホを手にするたびにその清らかなイメージに触れることで、無意識のうちに浄化のエネルギーと同調し、おんしゅだしゅだの効果を日常的にサポートしてくれるでしょう。
実践する際に知っておきたい注意点
おんしゅだしゅだは、心身に素晴らしい恩恵をもたらしてくれる可能性を秘めたパワフルな真言です。
しかし、その力を正しく、そして安全に受け取るためには、いくつか知っておきたい注意点があります。
実践を始める前に、ぜひ一度目を通しておいてください。
現実逃避の道具にしない
最も大切な注意点です。
仕事や人間関係で困難に直面したとき、真言を唱えることで一時的に心が安らぐのは良いことです。
しかし、真言に没頭するあまり、向き合うべき現実の問題から目を背けてしまうのは本末転倒です。
おんしゅだしゅだは、あくまで現実をより良く生きるための「心の筋トレ」や「エネルギー補給」と捉えましょう。
心を整えたら、現実世界でのアクションを起こす勇気を持つことが何より重要です。
過度な効果を期待しすぎない
「これを唱えれば、すぐに人生が好転するはずだ」といった過度な期待は、失望のもとになります。
効果の現れ方やスピードには個人差があり、非常に穏やかな変化であることも少なくありません。
「何も変わらないじゃないか」と焦らず、長期的な視点で、自分の内面の小さな変化に気づいてあげることが継続のコツです。
他者への強要は絶対にしない
自分が実践して良いと感じたとしても、それを他人に無理強いしてはいけません。
「あなたもこれを唱えるべきだ」といった態度は、相手への押し付けとなり、良好な人間関係を損なう原因になります。
スピリチュアルな実践は、あくまで個人の自由意志に基づくものです。
価値観は人それぞれであることを尊重し、自分の内側で静かに実践しましょう。
精神的に不安定な時は慎重に
心が極端に落ち込んでいる時や、精神的に非常に不安定な状態にある時は、自己流での実践は慎重に行うべきです。
真言によって内面の深い部分が刺激され、かえって感情が揺さぶられてしまう可能性もゼロではありません。
もし精神的な不調を感じる場合は、まずは専門の医師やカウンセラーに相談することを最優先してください。
その上で、補助的な手段として真言を取り入れるかどうかを判断しましょう。
宗教的な背景を理解する
おんしゅだしゅだは、仏教、特に密教という宗教的な背景を持つ言葉です。
特定の宗派に属する必要は全くありませんが、そのルーツに敬意を払う心を持つことは大切です。
軽い気持ちで面白半分に唱えたり、言葉を歪めて使ったりすることは避け、「聖なる言葉をお借りしている」という丁寧な気持ちで向き合うことをおすすめします。
これらの注意点を心に留めておくことで、おんしゅだしゅだはあなたの人生にとって、より安全で心強い味方となってくれるでしょう。
【知識編】おんしゅだしゅだの由来と知られざる意味


さて、実践的な方法を理解したところで、この章では「おんしゅだしゅだ」という言葉の持つ、より深い背景知識に迫っていきましょう。
なぜ、この短い言葉にこれほどの力が宿るとされるのか?そのルーツであるサンスクリット語の本当の意味、そして弘法大師・空海へと繋がる壮大な歴史の物語を紐解いていきます。
この知識編を読み終える頃には、あなたが唱える一言ひとことに、さらなる深みと確信が加わるはずです。
まずは、この不思議な響きの言葉がどこから来たのか、その語源から探っていきましょう。
「おんしゅだしゅだ」の語源とサンスクリット語の本当の意味
不思議な響きを持つ「おんしゅだしゅだ」という言葉。
これは一体どこから来たのでしょうか?そのルーツを辿ると、古代インドで使われていた神聖な言語、サンスクリット語に行き着きます。
この言葉は、3つのパーツに分解することで、その深い意味を理解することができます。
「おん(唵)」:宇宙の始まりを告げる聖なる音
最初の「おん」は、サンスクリット語の「オーム(Aum / ॐ)」という音を漢字で音写したものです。
「唵」という漢字が当てられることもあります。
「オーム」は、仏教やヒンドゥー教において、宇宙の創造から維持、そして破壊と再生のすべてを内包する、最も神聖な音(聖音)とされています。
祈りや瞑想、マントラの冒頭に唱えられることが多く、これを唱えることで、意識を宇宙の根源的なエネルギーに繋げるという意味合いがあります。
いわば、「おん」はこれから始まる神聖な儀式や祈りの開始を告げる「スイッチ」のような役割を持っているのです。
「しゅだ(修達)」:清らかさを意味する言葉
続く「しゅだ」は、サンスクリット語の「シュッダ(śuddha)」という単語の音を写したものです。
この「シュッダ」には、以下のような意味があります。
- 清浄な、純粋な
- 汚れのない、潔白な
- 明るい、輝かしい
つまり、「しゅだ」という音は、物理的な汚れだけでなく、精神的な穢れやネガティブなエネルギー、心の曇りなどを洗い流し、本来のピュアで輝かしい状態に戻すという、強力な浄化の意図が込められた言葉なのです。
「しゅだ しゅだ」:浄化の力を強調する繰り返し
では、なぜ「しゅだ」を2回繰り返すのでしょうか?
これは、サンスクリット語の文法的な特徴の一つで、言葉を反復することで、その意味を強調する効果があります。
「しゅだ、しゅだ」と重ねることで、「徹底的に浄化する」「完全に清らかになる」といった、浄化の力を最大限に高める意図を表しているのです。
漢字表記は「修達修達」だけではない?
日本語で表記される際、「修達修達」という漢字が使われることがありますが、これはあくまで音に対する当て字の一つです。
他にも「修唎修唎(しゅりしゅり)」など、似たような浄化の意味を持つ真言と混同されたり、宗派や流派によって異なる表記がされたりすることもあります。
大切なのは漢字の意味そのものよりも、「おん・しゅだ・しゅだ」という音の響きと、その背後にある「宇宙の力で、徹底的に浄化する」という本来の意味を理解することです。
この知識を持って唱えることで、真言が持つ力をより深く、そして明確に感じることができるようになるでしょう。
善無畏三蔵から空海へ。密教における歴史的つながり


「おんしゅだしゅだ」という真言は、特定の経典に出典がないため、その正確な起源は謎に包まれています。
しかし、一説には8世紀のインド出身の高僧、善無畏三蔵(ぜんむいさんぞう)が伝えたものだとされています。
そしてこの善無畏三蔵は、日本の仏教史におけるスーパースター、弘法大師・空海と、時代を超えた深い「師弟の系譜」で繋がっているのです。
密教を中国へ伝えた偉大な師、善無畏三蔵
善無畏三蔵(本名:シュバカラシンハ)は、もともと東インドの王族でしたが、王位を捨てて出家し、密教の奥義を究めました。
その後、高齢になってから海を渡って唐(当時の中国)へ赴き、皇帝の命を受けてサンスクリット語の密教経典『大日経』などを漢訳した、まさに中国密教の礎を築いた人物です。
彼が伝えた密教は、単なる哲学や思想ではなく、真言(マントラ)や印(手印)、観想(イメージ)といった具体的な実践(三密修行)を通じて、誰もがこの身このままで仏になれる(即身成仏)と説く、画期的な教えでした。
善無畏の教えを受け継いだ、空海の師・恵果阿闍梨
善無畏が中国で広めた教えは、多くの弟子たちに受け継がれていきました。
その教えの系譜に連なるのが、恵果阿闍梨(けいかあじゃり)という高僧です。
恵果は、善無畏が伝えた『大日経』系の密教と、別の流れを汲む『金剛頂経』系の密教という、当時二つに分かれていた密教の流れを統合した、非常に重要な人物でした。
そして、全ての教えは空海へ
西暦804年、日本の若き僧侶・空海は、この密教の真髄を求めて唐へ渡ります。
そして運命に導かれるように、長安で恵果阿闍梨と出会うのです。
恵果は空海を一目見るなり、その類まれなる才能を見抜き、「私が長年待ち望んでいた弟子が、ついに来た」と大変喜んだと言われています。
そして、自身が持つ密教の全ての奥義を、わずか数ヶ月という異例の短期間で空海に授けました。
これを「伝法阿闍梨位(でんぽうあじゃりい)の灌頂(かんじょう)」と言います。
この時、恵果から空海へと受け継がれた教えの源流を辿っていくと、その大元の一人として、善無畏三蔵の存在が浮かび上がってくるのです。
【 教えの流れ(系譜) 】
善無畏三蔵 → (多くの弟子) → 恵果阿闍梨 → 空海(弘法大師)
つまり、「おんしゅだしゅだ」が善無畏三蔵によって伝えられたという説が正しければ、それは空海が日本にもたらした真言密教のルーツと深く関わる、由緒正しい言葉であると言えるでしょう。
空海自身がこの真言を直接広めたという記録はありませんが、その思想の根底には、間違いなく同じ密教の精神が流れているのです。
真言密教・弘法大師 空海について
→高野山真言宗総本山金剛峯寺ホームページ
真言・マントラとしての特徴と分類


「おんしゅだしゅだ」は、スピリチュアルな実践において「真言(しんごん)」や「マントラ」と呼ばれます。
この二つの言葉は、しばしば同じ意味で使われますが、その背景や特徴にはどのような違いがあるのでしょうか。
「真言」と「マントラ」は基本的に同じもの
まず結論から言うと、「真言」と「マントラ」は、指し示すものは基本的に同じです。
- マントラ(Mantra):
古代インドのサンスクリット語で、「思考」「文字」「歌」などを意味する “man” と、「道具」「束縛からの解放」などを意味する “tra” が組み合わさった言葉です。
つまり、「心を解放するための道具(言葉)」といった意味合いを持ちます。
ヒンドゥー教やヨガの世界でも広く使われる、より広範な概念です。 - 真言(しんごん):
この「マントラ」という言葉が仏教に取り入れられ、中国で翻訳された際に生まれた言葉です。
その意味は「仏の真実の言葉」。
仏の悟りの境地や、その働きを象徴する言葉であり、それを唱えることで仏と一体になれるとされています。
特に空海が伝えた密教において、非常に重要な役割を果たします。
つまり、「マントラ」という大きな枠組みの中に、仏教的な意味合いを強く持たせたものが「真言」と理解すると分かりやすいでしょう。
「おんしゅだしゅだ」はどのような特徴を持つ真言か?
世の中には数多くの真言・マントラが存在しますが、その中で「おんしゅだしゅだ」は、以下のような特徴を持つと言えます。
- 短い(短呪・心呪):
真言には、お経のように長い「陀羅尼(だらに)」と、「おんしゅだしゅだ」のように短いフレーズの「短呪(たんじゅ)」や「心呪(しんじゅ)」があります。
短いフレーズは覚えやすく、日常の様々な場面で唱えやすいため、初心者でも実践しやすいのが大きなメリットです。 - 意味より「音」を重視する:
もちろん言葉の意味も大切ですが、真言・マントラはそれ以上に「音の響き(波動)」そのものに力があるとされています。
サンスクリット語の原音をそのまま音写しているのはそのためです。
言葉の意味を完全に理解していなくても、ただその音に意識を集中させて唱えるだけで、心身にポジティブな影響がもたらされると考えられています。 - 特定の仏に限定されない「概念的な」真言:
多くの真言は「不動明王の真言」「観音菩薩の真言」といったように、特定の仏様や菩薩様と結びついています。
しかし、「おんしゅだしゅだ」は「浄化」という概念そのものに働きかける、より普遍的な性質を持っています。
そのため、特定の信仰を持たない人でも、スピリチュアルな浄化のツールとして受け入れやすいという特徴があります。
このように、「おんしゅだしゅだ」は、数ある真言の中でも特にシンプルで、実践的、そして普遍的な性格を持った、現代人にとっても非常に扱いやすいマントラであると言えるでしょう。
一般人が唱えても大丈夫?よくある質問(Q&A)
ここまで「おんしゅだしゅだ」の魅力や背景について解説してきましたが、いざ実践するとなると、まだいくつかの素朴な疑問や不安が残るかもしれません。
ここでは、そうした「よくある質問」にお答えする形で、最後の懸念点を解消していきましょう。
- 仏教徒でなくても唱えていいの?
-
結論から言うと、全く問題ありません。むしろ、心の平穏を求めるすべての人に開かれた言葉です。
真言は、特定の宗派に属する人だけのものではありません。
特に「おんしゅだしゅだ」のように普遍的な浄化を目的とする言葉は、人種や宗教を超えて活用することができます。
「仏の真実の言葉に触れたい」という純粋な気持ちがあれば、誰が唱えてもバチが当たるようなことは決してありませんので、ご安心ください。
- 唱えてはいけない場所や時間は?
-
厳密に「唱えてはいけない」とされる場所や時間はありません。
しかし、TPOをわきまえる心遣いは大切です。
公の場で突然大声で唱え始めたり、仕事中に上の空で唱えたりするのは、社会的なマナーとして適切ではありませんよね。
理想は静かな自室などですが、それが難しい場合は、周りに迷惑がかからないよう心の中で静かに唱える(心念)のがおすすめです。
あなたの心の中は、誰にも邪魔されない最も神聖な空間です。
- 他のおまじないや真言と混ぜても平気?
-
複数の真言やおまじないを実践すること自体が悪いわけではありません。
しかし、特に初心者のうちは、意識が分散してしまい、かえって効果が薄れてしまう可能性があります。
まずは「おんしゅだしゅだ」ならそれ一つに絞り、じっくりと向き合う時間を作ることをお勧めします。
その言葉が持つエネルギーを深く感じられるようになってから、他の実践を取り入れると、より相乗効果が期待できるでしょう。
- 効果が感じられないのは、やり方が間違い?
-
「何も変わらない」と感じても、焦る必要はありません。
効果の現れ方には個人差があり、やり方が間違っているわけではないケースがほとんどです。
効果は「心のコップに水が溜まる」ようなもの。
一滴一滴は目に見えなくても、続けていればいつか必ず満たされ、あふれ出す瞬間が来ます。
結果を急がず、「ただ唱える」という行為そのものを楽しむくらいの気持ちで、気長に続けてみてください。
【まとめ】おんしゅだしゅだで心身を整えよう
この記事では、謎多き真言「おんしゅだしゅだ」について、その効果から正しい唱え方、歴史的背景までを深く掘り下げてきました。
最後に、その重要なポイントを改めて整理しておきましょう。
- 強力な「浄化」の真言: 「おんしゅだしゅだ」はサンスクリット語で「宇宙の根源の力で、徹底的に浄化する」という意味を持つ、心・身体・エネルギーを清めるための言葉です。
- 効果は多岐にわたる: 心のストレスやネガティブな感情を洗い流すだけでなく、波動が整うことで結果的に金運アップや願望実現を引き寄せやすくする効果も期待できます。
- 「嘘」の噂は誤解から: 「出典不明」であることや「過度な効果の誇張」が原因で嘘だと言われることもありますが、大切なのはあなた自身が心地よいと感じるかどうかです。
- 正しい唱え方はシンプル: 静かな場所でリラックスし、「おん・しゅだ・しゅだ」と一音ずつ丁寧に、心地よいペースで繰り返すのが基本です。回数は3回や7回から始め、慣れたら108回などに挑戦してみましょう。
- 一般人でも実践OK: 宗教や宗派に関わらず、誰でも安心して唱えることができます。大切なのは、言葉の背景にある文化への敬意を持つことです。
- 依存せず、補助ツールとして: あくまで現実をより良く生きるための「心のサプリメント」と捉え、日々の生活に前向きなエネルギーを取り入れるツールとして活用しましょう。
「おんしゅだしゅだ」は、魔法の杖ではありません。しかし、日々の実践を重ねることで、あなたの内側に静かで揺るぎない中心軸を育て、変化の多い現代社会を軽やかに生き抜くための、力強い味方となってくれるはずです。
まずは難しく考えず、今夜寝る前にでも、静かに3回唱えることから始めてみませんか?
その小さな一歩が、あなたの心をより澄み切った状態へと導く、大きなきっかけになるかもしれません。
【次のステップへ】あなたのタイプ別・おすすめアクション
💬 悩みを「話して」手放したいあなたへ
\ プロの力で心のモヤモヤをスッキリ解消! /
🧘 自分で「整える力」を身につけたいあなたへ
\ 一生モノのスキルで、ブレない自分軸を作る /
💎 運気を「守り」良い流れを維持したいあなたへ
\ 浄化した最高の状態を、お守りでキープ /